アニメと花言葉 -花言葉と作品の読解について考えること-
はじめに~花言葉と読解~
昨今、ファンシーンにおけるアニメなどの作品読解において、花言葉が用いられるのを見かけることがある。
例えば、アニメのとあるシーンでなんらかの花が象徴的に画面に映されたとする。そこで、その花が何の花であるかを特定して、その花言葉を調べる。そうして導き出された言葉こそが、制作陣から我々受け手側に提示された隠れたメッセージであると捉え、そのシーンの隠れたメッセージを味わう……というような流れである。
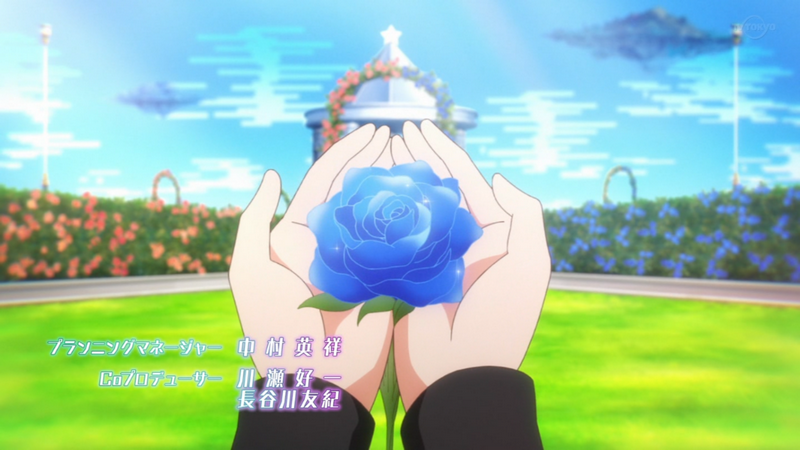
『絆のアリル』OPより。青いバラの花言葉は「夢がかなう」「神の祝福」1
しかしながら、私的にはこれの読解を何も考えずに行ってよいものか、という迷いがここしばらくあった。
実際私も「ここで提示された植物には何かメッセージが込められているのではないか」と、アニメに登場する花言葉が気になって調べることがある。現代のインターネットというのは親切なもので、調べると大抵その花の花言葉が何か、ということを解説してくれるサイトが見つかる(そもそも草花に詳しくないので何の花か特定するのが一番大変である)中でも特に親切なサイトだと「こうこうこういう由来があるのでこの花言葉なんですよ」と教えてくれたりもする。なるほどわかりやすい。
とはいえ、それをそっくり素直に受け取ってアニメの読解に還元していいものか? と、いささか考えてしまうことがあるのだ。
まず、インターネットに出てくる……というかインターネットに限らず花言葉というものが、どうも明確に制定されているものではないらしい、という点である。ちょっと調べて出てくるようなものは、ある程度信用のできるものが集められていると思うのだが、どうしても引用しようとすると、少しもやっとしたものを感じてしまう。
更に、そもそも同じ花でも花言葉に種類がある。手元にある『美しい花言葉*花図鑑』(著:二宮考嗣)を引いてみると、例えばキンモクセイの花言葉は「謙虚」「真実の愛」「初恋」「陶酔」「気高い人」であると言う。2アニメでキンモクセイが登場したとして、どの言葉を用いて読解すべきだろうか? 「ここで『陶酔』は話の流れ的におかしいから、『真実の愛』かもしれない」のように読解パズルをしてもいいかもしれないが、このように"答え合わせ"をしようとするのも、どうにもナンセンスであるように思えてしまう。それは花そのものを無視して、言葉だけを見出そうとしていないか? と感じてしまうからである。
それでもなお、花言葉というのは魅力的である。インターネットの花言葉解説サイトの画面がスクリーンショットとして切り取られ、その発信がSNSで拡散していく様が、花言葉の魅力を物語っているように思える。花から連想される美しき言葉たちは、アニメを彩る素晴らしいメッセージとして人々の感動を誘う。
しかし、同時にわたしたちはその美しさに魅了されきって、作品に向き合う前に、メッセージそのものにうっとりと陶酔してしまっているのではないか、とそう思ってしまう部分もあるのだ。
そんなこんなで、作品読解につきまとう花言葉との距離感というのは、地味に長年私を悩ませるものであった。
私は花言葉に関する本を数冊所持しているが、参照元として本を買ってみたのも、花言葉についてしっかりと知りたい、そしてインターネットより書籍のほうがいくらかは信用できるだろうと考えているからだ。
ところで、花言葉自体にはそれなりに歴史があるようで、ネットで由来を調べると「17世紀のオスマン帝国(現在のトルコ)の「セラム」という風習から」というような解説がしばしば登場する。3
また「世界ではじめての花言葉辞典」と謳われ最近和訳本が出た『花々の言葉』(著:シャルロット・ド・ラ・トゥール婦人 訳:三宅京子)では、人が花々の裏に言葉を忍ばせるということの普遍さが説かれていて、セラム以外の花々と人との関わりについて書いている。
中世の書物、花々による表象で満ち溢れている。たとえば、ペストフォレの物語では、バラの花で編まれた帽子が恋人たちの宝物であると語られる。(中略)中国人は、花に枝葉と根を組み合わせて花文字をつくる。エジプトの石片には、数々の異国の植物が象形文字となって刻まれ、この国が応じに重ねた征服の成果を伝えている。
花言葉は、つまり、世界と同じだけの古い歴史を持つ。しかも、古びることはないだろう。春が巡ってくれば、そのたびに新しい文字が書き加えられていくからだ。『花々の言葉』 序文 p14-15
花という存在に対し、人々の手によってで蓄えられた文脈によって、確かに花には共通の言葉というものが見いだせるのだろうと思う。
それはいわゆる花言葉でもあり、そしていわゆる花言葉でないものもある。今回はアニメという媒体で、花がその裏に言葉を持つモチーフとして用いられるシーンをいくつか拾い上げながら、アニメ読解と花言葉の距離感について考えたことを、とりとめもなく書いていきたい。
『ひなろじ ~from Luck & Logic~』と花
アニメによっては作中に花言葉が登場するものがある。当たり前だが、その場合は花言葉と描写のパズルめいた読解に悩むことはない。というか、作中の言葉を受け取るのであれば読解の必要もない。
『ひなろじ~from Luck & Logic~』というアニメにおいては、白のダリアが「感謝」を表すものとして登場する。
4話にて、お世話になった先輩である夕子の誕生日プレゼントに悩むリオンは、自身の花を生み出すという能力によって白のダリアを生み出し、それを「ありがとう」の言葉と共に夕子に贈る。花言葉がもっとも意識される瞬間のひとつは、花を贈り物として渡す時であろうから、アニメにおける花言葉が使われるシーンとしても、かなり王道と言えるだろう。夕子がもらったダリアの花を後輩たちに贈り返すのも含め、花にまつわるあたたかなエピソードである。
ちなみに、ここで試しに、『花言葉*花図鑑』を見てみると、ダリアの花言葉は「華麗」「気品」「優雅」「移り気」であると言う。本書によると「ナポレオンの王妃ジョセフィーヌが愛した植物として、バラと共に有名になりました。(中略)花言葉は美しい花姿から名付けられていますが、『移り気』のみは、気まぐれな気性だったジョセフィーヌに由来しているようです。」とある。4ネットを見ると確かに白のダリアには「感謝」と書かれているものがあるが、その由来は明らかになっていないそうである。5
アニメの作中ではっきりと「感謝」を示す花として登場しているので、ここでの読解には迷う要素はないのだが、しかしここにはモチーフとして登場した花に、わたしたちが何の言葉を当てはめるかの難しさがあるのではないかと思う。
そういう意味では、はっきりと花に何の言葉を託しているのか明言するのは、さりげなさを失うと同時に、ある意味での誠実さがあるとも言えるかもしれない。贈り手と受け手、双方が込められたメッセージをわかちあっているのが、贈り物にとっては幸福な状態だろう。

『ひなろじ ~from Luck & Logic~』3話より。夕子に花束を贈るリオン
花言葉を用いる読解が適切でないと思われる時もある。
ひなろじの11話は屈指の百合・ギャグ色が強い異色回。キューピットの矢の能力によって催淫めいた状態に陥ったニーナが、リオンに「好き」と囁くシーンがある。この時、これみよがしにユリの花が画面に映されており、そして数カットの間で蕾から一気に開花までする、という現実的ではない動きをしている。
試しに、再びここで花言葉での読解を試みてみる。『花図鑑*花図鑑』によると白のユリは「純潔」「威厳」であると言う。6『花々の言葉』では、色を指定せずにユリの言葉は「威厳・荘厳・王位」とある。7また、ユリは西洋美術の象徴としてもよく用いられており、『西洋美術解読辞典』(著:ジェイムズ・ホール 監修:高階秀爾)によれば「純潔の象徴で、聖母マリアおよび童貞聖女らと深いつながりを持つ。」とある。8
これらを見ると、最初の花図鑑の通り第一に「純潔」第二に「威厳」とするのはユリのモチーフ読解としてはまっすぐな読みだろうと思われる。
だが、ひなろじにおけるこのシーンで、この読解はどちらも当てはまらないものと思われる。作中でも屈指の性的アプローチを連想させるこの回に「純潔」はそぐわないし、「威厳」というのもイマイチである。このユリの花の意図するところは、女性同士の親密な関係を意味するスラングであるところの「百合」にちなんだものと捉えるのが適切だろう。百合の花が開花したのは、「百合」が「開花」したということなのである。
極端な例ではあるが、頭ごなしに花に込められた言葉を花言葉から紐解くのが適切ではない例、と言えるのではなかろうか。

『ひなろじ ~from Luck & Logic~』11話より。様子を見守るように咲く百合の花
『鬼人幻燈抄』と花
2025年のアニメにおいて、わたしが最も評価されるべきアニメのひとつと考えているのがこの『鬼人幻燈抄』である。9
本作は江戸時代から平成に至るまでを描いた作品であり、アニメになっているのは江戸~大正の時代である。ちなみに『花々の言葉』がフランスにて刊行されたのは1819年とのことで、日本でいえば文政2年である。江戸時代が終わりに差し掛かり幕末へと向かう手前の時代であり、鬼人幻燈抄の舞台となっているのもまさにこのあたりの時代なのである。とはいえ、鎖国下の日本において、さらには一介の町人がこのフランスでのムーブメントを知る由もなく、いわゆる「花言葉」というものは存在しないと言って差し支えないだろう。
”花言葉"こそないが、本作には花に言葉を託すシーンが数多くある。たとえば3話にて、主人公の甚夜は、馴染みの蕎麦屋の娘・おふうと偶然出くわす。雪柳を眺めていたおふうは、その花について甚夜と話す。
おふう「桜を見ていました」
甚夜「これは柳だろう」
おふう「違いますよ。ほら、雪柳といいます。咲いた花の重さにしなだれる姿が、雪が積もった柳みたいでしょう? だから雪柳。でも、実際には柳ではなく、桜の仲間なんですよ」
甚夜「雪柳、か。桜には見えないな。桜でありながら柳を模し、柳に見えて柳ではなく。柳と桜、どちらにもなれない。雪柳は哀れだな」
おふう「でも、綺麗でしょう? 柳ではないけれど、桜として見られなくても。雪柳はとてもかわいらしい花を咲かせるんです」『鬼人幻燈抄』 3話より

『鬼人幻燈抄』3話より。雪柳の前に立つ甚夜とおふう
甚夜は雪柳を「どちらにも属さず哀れ」と評すが、一方でおふうは「雪柳には雪柳の可憐さがある」と甚夜に説く。ここで甚夜は鬼を狩る人間でありながらも片腕に鬼の腕を移植しており、鬼でも人間でもない中途半端な狭間の存在として、雪柳と自身の立場を重ねている。会話そのものの表層の話題は雪柳についての話であるが、自身のあり方に悩む甚夜と、それを解きほぐそうとするおふう、という構図が裏では見え隠れする。そしておふうは、この時点では鬼と人の甚夜の境遇を知らぬはずであるが、その語り口には何かを察するような雰囲気も微かに見え隠れするのである(おふうの境遇を思うと、この時点で察するものはあったのだろうと推察される)
この一幕は、直接的に甚夜のあり方について話すよりもずっと奥ゆかしくもあり、そして同時に相手の立場に踏み込みすぎないという距離感が、まだ双方の関係が浅いことを反映されているようでもある。花を介して表現することで、巧みな表現に成功していると言えるだろう。更に鬼人幻燈抄の江戸編の物語を知る人であれば、曰く付きの酒「なごり雪」の前にここで「雪」を連想させる花を登場させることには、過去の因縁にまつわる雪という象徴によって、さらなる味わい深さも感じられるであろう。苦しい過去、すなわち冬の時代を超えて今の生き方を選ぶ甚夜にとって、雪柳が春に咲く花であることも意味を持つわけである。
そしてまさにこれは、直接言葉を贈られるよりも、花というヴェールにメッセージを包んで、奥ゆかしくそれを渡される方が魅力的に思える、ということに近いのではないだろうか。
ちなみに、ユキヤナギの花言葉は、その小さくかわいらしい花に着目して「静かな想い・愛らしさ・気まま」であると言う。10鬼人幻燈抄が雪柳に着目するのは、そのかわいらしさよりも「柳でも桜でもない」というところと、そして「春に咲く花」ということである。読解するにあたってユキヤナギの花言葉を愚直に当てはめようとしてもしっくりとはこないが、しかし本作の花の使い方から感じるのは、花言葉を巧みに操る存在の持つ、奥ゆかしい魅力である。
曖昧な告白をされると、愛の確証をもらうよりも遥かに人は心奪われる。そして、美辞を連ねた切々たる恋文より、花束をひとつ贈ることで幸せをつかむ男の姿を私はよく目にしてきた。
『花々の言葉』 序文 P16
おふうと甚夜の花にまつわるシーンはいくつかある。沈丁花のシーンはアニメでも非常に心に残るシーンであった。
おふう「名前、わかります?」
甚夜「いや」
おふう「沈丁花。秋につぼみをつけて、冬を越して春に咲きます」
甚夜「香りが強いな」
おふう「いい匂いでしょう? 沈丁花は春の訪れを告げる花なんです」『鬼人幻燈抄』 4話より
4話にてふと道端に咲く沈丁花について、おふうは甚夜に話している。
そして後の13話。とある冬のシーンに、再びこの沈丁花の花の名前が登場する。
おふう「甚夜くん。沈丁花、覚えていますか?」
甚夜「……覚えている。凍える冬を超えて咲く花。春を告げる花。……本当に、世話になってばかりだ」『鬼人幻燈抄』 13話より

『鬼人幻燈抄』13話より。言葉を交わす甚夜とおふう
13話。木々も枯れた寒々しい冬の光景は、凄惨な出来事を経て、暗く沈む甚夜の心の内を反映させたかのように感じられる。そんな甚夜に、おふうは別れ際に一言「沈丁花、覚えていますか?」とだけ問う。甚夜はそこに込められた「凍える冬を超えて咲く花」という励ましの想いを受け取り、一人静かに感謝の意を呟くのである。
ジンチョウゲの花言葉は「永遠・不滅・不死・栄光」らしく、常緑樹であることがこの由来であると言う。11花言葉と劇中で話す内容は異なるが「秋につぼみをつけ、冬を超え、春に咲く」というジンチョウゲの生態から導き出されていることには共通点がある。
鬼人幻燈抄の鬼は悠久の時を生きるので、江戸から幕末を経て、平成の世に至るまで甚夜の物語は続いてゆく。そんな中で路傍に咲く可憐な花というのは、季節の移り変わりを教えるものであり、時間がもたらす変化を示すものであり、そして新たな再生の芽吹きを感じさせるものである。鬼の生きる長い時間と、生まれては死ぬ人の時間は一見交わらないが、作中にて度々登場する花によって、甚夜の心の変化が巧みに表現されている。見事な花のモチーフの使い方だと思う。
もちろん、可憐な花そのものが、殺伐とした鬼を切る戦いの日々とは相反する穏やかな日常を感じさせるものとして、視聴者の心を癒やすのもまた、花のもたらす見事な演出効果であろう。
さて、鬼人幻燈抄の花にまつわるエピソードとして、ひときわ印象的エピソードがある。アニメ16話にて、人を食う鬼が出るとの噂を聞きつけて廃寺を訪れた甚夜は、巨大な狐のような鬼と対峙する。容赦なく鬼を圧倒する甚夜は普段通りその鬼の力を吸収しようとするが、気がつくといつもの蕎麦屋に戻っていた。そしてそこには子どもを連れて甚夜の妻を名乗る、夕凪という遊女がいたのだった……。
夢か現かのようで、まさに狐につままれたような心地のする異色な回である。甚夜は夕凪一見他愛もない話をしながら共に1日を過ごし、そしていつしか日は傾きはじめる。夕暮れ時、2人は川辺にたどり着いて、そこに咲く白粉花について話をする。
甚夜「白粉花だな、夕化粧や野茉莉という別名もある」
夕凪「白粉花? 黄色や赤もあるけど?」
甚夜「種子の皮の中に白い粉が入っている。それを子どもが化粧遊びに使うからだそうだ。そして白粉花は、なぜか夕方から花を咲かせ始める」
夕凪「詳しいじゃないか」
甚夜「受け売りだ」
夕凪「でも、不思議な花だね。夕方から咲き始めるなんて」『鬼人幻燈抄』 16話より

『鬼人幻燈抄』16話より。一面の白粉花の中に佇む甚夜と夕凪
夕暮れ時のロケーションを絶妙な色彩設計で雰囲気たっぷりに演出するこの回は、映像作品としての本作の持つ実力を感じさせるものである。
夕凪は「子どもが嫌い」といいつつも、しかし大切に子どもを抱きかかえる。そもそも、甚夜の妻というのも当然偽りなのである。飄々とした様子を見せながらも、その実非常に愛情深い、そんな夕凪という女性は、様々な嘘を持っているのだ。
そしてそんな彼女の姿を魅力的に装飾するのが、このシーンに登場する白粉花である。夕方という昼と夜の曖昧な時間に咲く白粉花。それは本心をなかなか見せない夕凪のようである。由来であるという「化粧遊び」すなわち偽りの化粧であることもまた、白粉で顔を装飾する遊女の嘘とつながりを見いだせる。このエピソードでは白粉花にまつわる会話が、結末(一応ここでは伏せるが)に至るまで、すべて見事に物語へと吸収されていく。非常に魅力的な、花に関わる言葉に溢れたエピソードだと言えるだろう。
オシロイバナの花言葉は「臆病・内気」であるという。この由来は「暑い夏の日の夕方にひっそりとラッパ状の花を咲かせる様」から来ているそうだ。12鬼人幻燈抄のこのエピソードと、そして花言葉はそれだけ見ればあまり一致はしないが、しかしオシロイバナの生態の何に着目しているか、という点では共通点も見られる。
これは、どちらも元を辿れば、連想のもとはオシロイバナという花であるからだろう。花言葉がオシロイバナから「臆病・内気」という言葉を導きだすことができるように、物語もオシロイバナから、嘘と偽りにまつわる美しきエピソードを導き出すことができる。実はここには近い営みがあるのではないか、と思う。
おわりに~新たに萌え出る花言葉~
もともと花言葉を用いての読解について思うところがあったので今回の記事を書き始めたのだが、調べていくうちに花言葉そのものの面白さということについても、改めて感じられるようになってきたように思う。
花言葉というのは元来その花のもつ生態や、あるいは逸話によって導き出されていくものであるという。そうした背景まで踏まえるならば、花言葉による読解は花そのものの読解に他ならない。花の咲く季節、色、文脈、そうした花そのものを捉えようとした時に、花言葉はその一助になるのかもしれない。
そして何よりも、そこに文字で「愛」と書かれるよりも、情熱的な赤いバラで彩られる方が純粋に魅力的ということは否定のしようがないだろう。
『花々の言葉』では、花言葉の紹介に加えて、花にまつわる様々な角度からのテキストが添えられており、時には詩人によっていかにしてその花が詠まれてきたのか、ということを紹介している。
言葉が花に花言葉を与え、そしてその繰り返しによって花には様々な言葉が加えられていく。冒頭で引用した『花々の言葉』の言葉を借りるならば「春が巡ってくれば、そのたびに新しい文字が書き加えられていく」ということなのだろう。
今回ここで紹介したアニメーション作品もまた、それを見た人にとっては花に新たなイマジネーションをもたらすものであろう。
おそらく私はオシロイバナを見た時に、夕凪のつく優しい嘘のことを思い出すことになる。書籍によって花に結びつけられる"花言葉"が時に異なるように、わたしたち一人一人が感じる花言葉というのも、いくつもあっていいはずである。
故に私は大真面目に普段話しているのだが、「俺だけ入れる隠しダンジョン、こっそり鍛えて世界最強」 をネモフィラの花言葉の末席に加えようとすることは、実に正当な主張なのではないだろうか? 『俺だけ入れる隠しダンジョン』を見たならば、かならずネモフィラの花はアニメエンディングテーマ『ネモフィラ』とともに連想されるに違いないからである。
ちなみに「俺だけ入れる隠しダンジョン、こっそり鍛えて世界最強」というのは、自分だけ入れる隠しダンジョンでこっそり鍛えることで世界最強になれるという、作品に登場するダンジョンを開く合言葉として用いられる印象的な言葉である。
ということで、今日は最後にこの花言葉を覚えていただきたい。
ネモフィラの花言葉は
「どこでも成功」
「俺だけ入れる隠しダンジョン、こっそり鍛えて世界最強」13

商品リンク
花々の言葉 世界ではじめての花言葉辞典 シャルロット・ド・ラトゥール夫人(著) 三宅京子(訳)
※楽天ブックス
美しい花言葉・花図鑑‐彩りと物語を楽しむ‐ 二宮 考嗣 (著)
西洋美術解読事典: 絵画・彫刻における主題と象徴 ジェイムズ・ホール (著), 高階秀爾 (監修)
【Amazon.co.jp限定】鬼人幻燈抄 Blu-ray BOX (特装限定版)(オリジナル特典 アクリルスタンド4種セット(甚夜、鈴音、おふう、秋津染吾郎))
鬼人幻燈抄 葛野編 水泡の日々【電子版特別短編付き】 中西モトオ (著)
本記事の画像は全て、以下作品より引用。
『絆のアリル』 ©KA/絆のアリルPJ ©絆のアリル製作委員会
『ひなろじ ~from Luck & Logic~』 ©Project Luck & Logic
『鬼人幻燈抄』©中西モトオ/双葉社・「鬼人幻燈抄」製作委員会
-
『美しい花言葉*花図鑑』著:二宮考嗣 p154 余談:『美しい花言葉*花図鑑』においてもバラは各色や本数に至るまで様々な花言葉が紹介されており、バラがいかに人々に愛された花であるかということを感じさせる。『花々の言葉』においても6月の花としてバラのみで全てのページを使い切っており、扱いの違いを感じさせる。 ↩︎
-
『美しい花言葉*花図鑑』著:二宮考嗣 p197 ↩︎
-
『美しい花言葉*花図鑑』著:二宮考嗣 p136 ↩︎
-
『美しい花言葉*花図鑑』著:二宮考嗣 p178 ↩︎
-
『花々の言葉』(著:シャルロット・ド・ラ・トゥール婦人 訳:三宅京子) p122 余談:本書では、ユリについて「他の花々に囲まれてこそ、他を圧倒する存在になる。まさに、王なのである」とある(p124) ちなみに、訳者解説によると「通常は『純潔』を表すユリもここでは専ら異なる象徴」(p344)とある ↩︎
-
『西洋美術解読辞典』(著:ジェイムズ・ホール 監修:高階秀爾) p352 ↩︎
-
余談:ネットの反響を見ていると、後半延期の末バトルシーンのアニメーションがかなりギリギリになってしまったために、駄作と貶められていることが多い。後半、アクション的に惜しさが残ってしまったのは事実であるが、それを差し引いても優れたところはいくつもあり、駄作と貶められるような作品ではないと強く思う。 ↩︎
-
美しい花言葉*花図鑑』著:二宮考嗣 p79 ↩︎
-
【ジンチョウゲの花言葉】怖い意味もある?プレゼントに贈っても大丈夫?(Green Snap STORE) ※『花言葉*花図鑑』には収録なし。 ↩︎
-
美しい花言葉*花図鑑』著:二宮考嗣 p107 ↩︎
-
アニメ『俺だけ入れる隠しダンジョン』楽しい作品なのだが、「ハーレム自慢大会」のような下品なお色気展開や「チューリップライオン」のような珍妙な展開があったりはするので、鬼人幻燈抄を紹介したテンションでそのままオススメするような作品ではないことだけは断っておきたい。故にジャンクな色が強い本作のエンディングテーマとして『ネモフィラ』の曲はかなりギャップがあったのだが、アニメ終盤でオリヴィア師匠の境遇が掘り下げられた時に、まさにこの歌詞がぴったりと当てはまる展開で驚いたことは印象深い。『ネモフィラ』では冬を超えて春に咲く、青空を思わせる花としてネモフィラが歌われている。更に余談ではあるが「どこでも成功」というのは『IDOLY PRIDE』にてネモフィラの花言葉として紹介された言葉である。 ↩︎